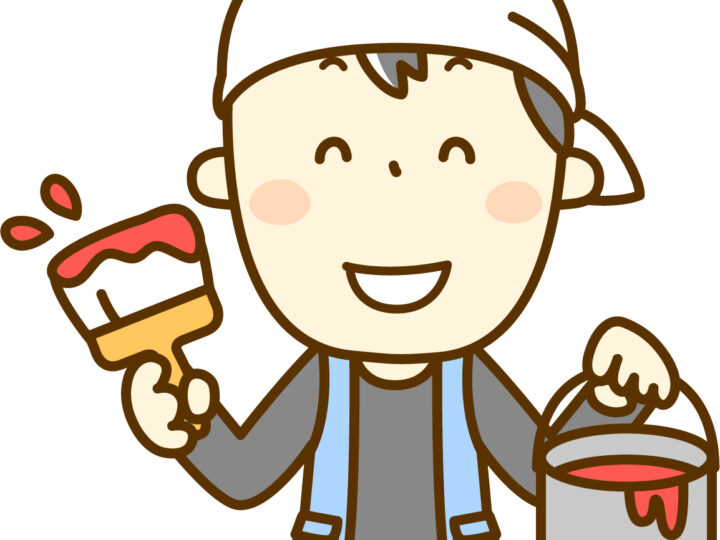塗装のベストな時期💮そろそろ外壁塗装をお考えのあなたに必見です! l京都市、宇治市、八幡市の外壁塗装&屋根塗装&雨漏り専門店【塗り達】
2022年9月21日 公開
「そろそろ外壁塗装をしたいと考えてはいるけれど・・・いつがいいんだろう?」
と悩まれている方も多いと思います。
塗装工事は、決して安い買い物ではありません。
みなさまにとって大切なお住まい、
1番良い時期に塗装をしてあげたいですよね🏠
今回は、そんな外壁塗装のベストな時期・季節についてお話したいと思います![]()

塗装工事について、まず前提として知っていただきたいのが
💮基本的に、年中行うことが可能💮
ということです。
雨が続く梅雨の時期や、積雪のある冬の季節に塗装工事をすることは難しいのでは?
と思う季節でも、しっかりと注意点を守っていれば可能なのです💡
塗装工事の一般的な条件
💮気温15℃~30℃
💮湿度75%以下
上記の条件は、塗料の硬化・乾燥に適しています。
そのため、塗装工事に問題が生じる事はないと考えられます。
また、塗装工事期間中は、窓やエアコンの室外機などを養生することになります。
エアコンをつけることなく、窓を開けなくても過ごしやすい季節であれば
工事期間中を無理なく過ごすことができますので、
これらの条件を満たした季節が最も塗装工事に好ましい季節といえるでしょう。
しかし、塗装工事が可能な条件があるなら、塗装工事が出来ない条件もあります。
![]() 気温が約5℃以下のとき
気温が約5℃以下のとき
![]() 湿度が約85%以上のとき
湿度が約85%以上のとき
![]() 雨や雪が降っているとき
雨や雪が降っているとき
![]() 結露や霜が発生しているとき
結露や霜が発生しているとき
上記の状態のときには、塗料が乾かなかったり、
せっかく塗布した塗膜が、雨や雪で流れ落ちてしまうからです。
【季節ごとのメリットとデメリット】
春(3月~4月ごろ)
春は湿度が低く、塗料が乾きやすい気候が続きますので塗装工事がスムーズに進みます。
雨が降ることも少ないので、窓を閉め切っても過ごしやすいですし、
塗装工事が予定通りに進みやすいともいわれています。
砂埃が黄砂などのゴミが付着してしまう事があります。
依頼が集中しますので、希望の予定で工事を進められないこともあります。
梅雨の時期(6月~7月ごろ)
適度な湿度を守ることで、問題なく塗装工事を進めることが出来ますが、
雨が降ってしまうと工事期間が延びてしまいがちなところもあります。
夏(8月ごろ)
夏は塗料の乾きが早いのです。
そのためスケジュ-ル通りに工事が進みやすいですが、
窓を開けられないので非常に暑くなります。
また、突然の夕立がくると作業がストップしてしまうのは難点です。
塗料の乾きは早いので、工期が大幅にずれてしまうことは
ほとんどないでしょう。
秋(9月~11月)
秋は湿度が低く、塗料も乾きやすい季節です。
そのため工事がスムーズに進みやすいです。
ただ、台風の発生が多い季節でもあるので工事期間が延びてしまったり、
予約が集中して希望の予定が組めないケースもあります。
秋は、春と同じで塗装工事の依頼が多く人気の季節ですので、
工事をご検討の方は、早めに工事日程を立てるといいでしょう。
冬(12月~2月)
エアコンを使用しなければ、窓を閉め切っていても暖房器具で過ごすことが可能です。
気温が低すぎると工事はできないので、
天候・気温には気を使いながら進めます。
そのため工事期間が延びてしまう事が多々あります。

いかがでしたか??💡
条件を守っていれば、1年中塗装工事は可能です。
そして塗装工事を行う人気の季節は、春と秋です💮💮
人気の季節に塗装工事の予定を組まれるのも
もちろんアリですし、
外壁の状態などを考慮したうえで、
お客様のお住まいに合った時期に塗装工事を行うことも大切だと思います。
どうぞ、ご参考にしていただけると幸いです。