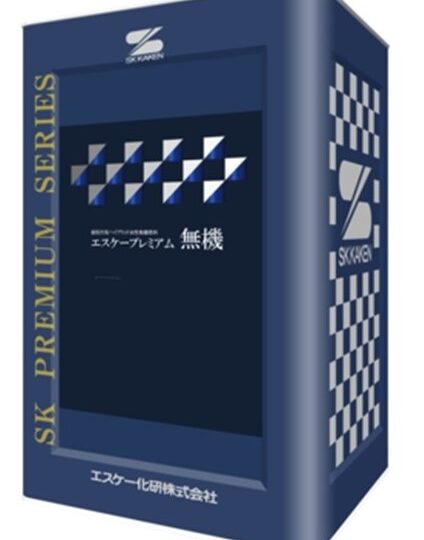2022年8月8日 更新!
屋根・外壁塗装で、下塗り塗料が吸い込まれてしまう?! l京都市、宇治市、八幡市の外壁塗装&屋根塗装&雨漏り専門店【塗り達】
2022年8月8日 公開 屋根・外壁塗装を行う際に、 塗料が建材に吸い込まれてしまう現象があるのをご存知でしょうか。 砂地に水を撒いた瞬間、水が砂に吸い込まれていくように、 塗料を塗ると建材に吸い込まれてしまうことがあるのです。 塗装を行う際、 上塗りの塗料を塗布する前に必ず「下塗り材」と呼ばれる塗料を塗布します。 下塗り材には、上塗り塗料の「吸い込み」を抑えてくれる働きがあるのですが、 そもそも「吸い込み」とは何なのでしょうか? 建材が塗料を吸い込んでしまうのはいけないことなのか? また、吸い込みを抑えることで、どんなメリットがあるのでしょうか? 今回は、塗料が建材に吸い込まれてしまう現象 「吸い込み」について、お話ししたいと思います。 建材に塗料が吸いこまれてしまうのは何故か? ここで、屋根のカラーベストという屋根材を例に、お話ししたいと思います。 カラーベストというスレート屋根は、建材自体にはほとんど防水性能がありません なので、新築から10年もすると、 経年劣化で防水性能が失われていき、雨水などが内部へ侵入してしまいます そして、新築から20年も経過すると、 防水性能の低下から、屋根の表面をコケやカビが覆ってしまいます。 旧塗膜も脆弱なので、屋根一面が砂地のような状態になるのです。 塗装工事では、 まず、これらの汚れを高圧洗浄で綺麗に落としていきます。 画像の様な屋根は、経年劣化でほぼ防水性能が失われている状態です。 下塗り材も雨水と同様、液体なので この表面に下塗り材を塗布しても屋根材に染み込んでしまうのです。 下塗り材の目的とは? 防水性能が低下している建材に下塗り材を施しても 塗料が染み込んでしまうのであれば、 下塗り材を塗布する意味はあるのでしょうか?? そもそも 下塗り材を塗装する目的は、 上塗り材との密着性を高めることと、 屋根材に染み込ませて中で固まらせることによって、素地を強化させることです。 なので、下塗り材が染み込んでいくこと自体は良いことなのですが、 染み込んでしまった場所にそのまま上塗り材を塗装することはNGとされています。 もし、屋根全体がほぼ下塗り材を吸い込んでしまった状態で、 上塗り材を塗布してしまったら、、、 当然、下塗り材は上塗り材と密着せずに工事を終えてしまうので、 早期の段階で塗膜剥離を起こしてしまう事が予想されます では、建材が下塗り材を吸い込んでしまったらどうすれば良いのでしょう?? 単純にもう一度、下塗り材を塗装します。 各塗料メーカーが出している表現は異なりますが、 下塗り材の「吸い込みが止まるまで」、「濡れ感が出るまで」塗布します。 塗り達では、屋根の塗装をする際、 基本的に下塗り材を2回塗装しておりますが、 屋根材の状態をみて、下塗り材を3回塗装する場合もあります。 屋根の劣化状態に合わせて判断し、 早期塗膜剥離が起こらないよう最善を尽くしております ↓下塗りを2回している様子です★ #gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 50%; } #gallery-1 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-1 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */ いかがでしたか?? 下塗り材はただ塗ればいいという訳ではなく、 塗った後の建材の状態をみて、次の工程に進むことが大事なのですね 下塗り→中塗り→上塗りと3回塗装する工程が一般的にいわれておりますが、 必ずしも3回塗りが正解で キッチリした塗装業者であるということではありません。 施工前に現地調査を行い、 建材の劣化状態を見極め判断した上で、 工事を進めていく業者さんに依頼できると安心ですね。MORE