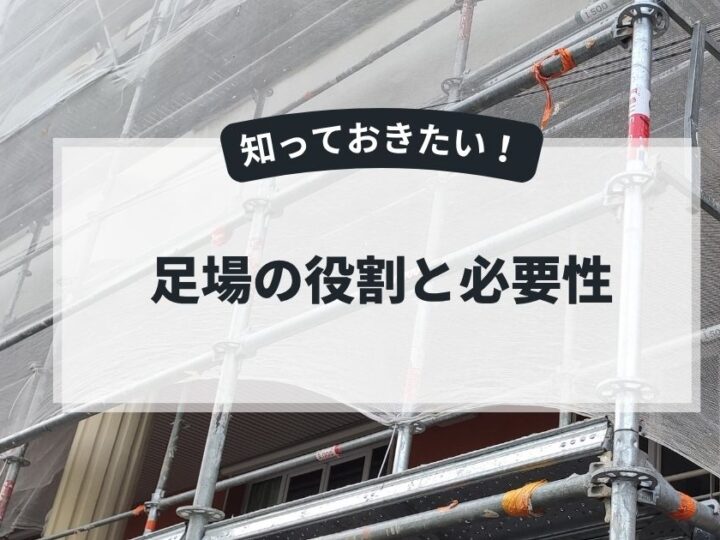外壁・屋根の塗装を始める前に知っておきたい7つの準備ポイント
~後悔しないために!工事前に知っておきたい大事なこと~
家の外壁や屋根の塗装を検討しているけれど
「何から始めればいいのか分からない…」という方は多いのではないでしょうか?
今回のブログでは、塗装工事の前に知っておくべき準備や注意点を、7つのステップに分けてわかりやすくご紹介します。
目次
- ① まずは「塗装が本当に必要か」をチェックしよう
- 🔍【セルフチェックまとめ】
- ☑「うちはどうだろう?」と思ったら…
- ② どんな塗装工事をするか目的をはっきりさせよう
- ③ 信頼できる塗装業者を選ぶコツ
- 業者選びのチェックポイント
- ワンポイントアドバイス
- ④ 塗料の種類と特徴を知っておこう(ざっくりでOK)
- 塗料の選び方のヒント
- ⑤ 色選びは慎重に!見本だけで決めない工夫
- 色選びの注意点
- シュミレーションを活用しよう
- ⑥ ご近所へのあいさつと、生活への影響も想定しよう
- 工事中に考えられること
- ご近所への配慮も忘れずに
- ⑦ 契約前にチェック!見積書と工事内容をしっかり確認
- 見積もりで確認すべきポイント
- ワンポイントアドバイス
- まとめ|塗装工事は「準備」が成功のカギ!
- 🔍 塗装工事は「ただ塗る」だけではなく、準備と確認で成功が決まります。
① まずは「塗装が本当に必要か」をチェックしよう
〜家のSOSを見逃さない!こんな症状が出ていたら要注意〜
外壁や屋根は、日々、雨・風・紫外線・気温の変化など、過酷な環境にさらされています。
そのため、見た目にはキレイに見えても、知らないうちに少しずつ劣化が進んでいることが多いのです。
「まだ大丈夫」と思っていても、以下のような症状が出ていたら、そろそろ塗装のタイミングかもしれません。
✅ チェック①:外壁を手で触ると白い粉がつく(チョーキング現象)
【 現象 】
外壁を軽くなでたときに、手に白っぽい粉がつく状態です。
【 原因 】
塗膜(塗料の膜)が紫外線などで劣化し、表面が粉状になっているサインです。
【 注意点 】
・見た目がきれいでも、防水性が低下している可能性あり
・このまま放置すると、雨水が壁の中に染み込み、内部から傷むリスクも
【 対処目安 】
→ チョーキングが起きていたら、塗装の効果が切れ始めていると判断し、早めのメンテナンスがおすすめです。
✅ チェック②:壁にヒビ(ひび割れ)がある(クラック)
【 現象 】
外壁に細いスジ状のヒビが入っている。場所によっては深く、目立つヒビも。
【 原因 】
乾燥・地震・建物の動きによって起こります。塗膜が硬くなっている場合も原因です。
【 注意点 】
・ヒビから雨水が侵入し、壁の中が腐食するおそれあり
・放置すると、内部の断熱材や木部にカビやシロアリ被害が起きることも
【 対処目安 】
→ 小さなヒビでも、幅0.3mm以上のクラックがある場合は要注意。
塗装前に補修が必要になるケースもあるため、専門業者にチェックしてもらいましょう。
✅ チェック③:外壁や屋根の色あせ・ツヤ消え
【 現象 】
塗装直後のツヤがなくなり、色が全体的にくすんできたように見える。
【 原因 】
紫外線や風雨によって、塗料の顔料が分解されて退色してしまうため。
【 注意点 】
・色あせは劣化の初期サイン。防水性が落ち始めている可能性あり
・塗料の性能(遮熱、防汚など)も低下している可能性があります
【 対処目安 】
→ 外観の美観を保ちたい方や、10年以上塗り替えていない場合は検討のタイミングです。
✅ チェック④:苔・カビ・黒ずみが目立つ
【 現象 】
特に日当たりの悪い北面や、屋根の一部に「緑っぽい苔」「黒いスス汚れ」のようなものが付着している。
【 原因 】
湿気や水分がたまりやすい場所に、空気中の胞子が付着して繁殖。
塗膜の防水・防汚性能が落ちている証拠でもあります。
【 注意点 】
・見た目が悪いだけでなく、素材の劣化を進める要因にも
・放置すると、カビ臭やアレルギーの原因にもなりかねません
【 対処目安 】
→ 洗浄だけでは根本解決にならない場合も。
塗膜の機能が失われているので、塗り替えと防カビ対策塗料の検討がおすすめです。
✅ チェック⑤:雨漏り・室内の天井や壁にシミがある
【 現象 】
屋根裏や天井に「濡れた跡」や「茶色っぽいシミ」がある。
壁のクロスが浮いている、めくれている、などの症状も。
【 原因 】
外壁や屋根の防水層が劣化し、雨水が建物内部に侵入している状態。
【 注意点 】
・ここまで進行している場合、塗装だけでなく補修・改修が必要なケースも
・構造部分の劣化が進行していると、工事費用が高くなる傾向があります
【 対処目安 】
→ 雨漏りが起きている=塗膜が完全に役割を果たしていない状態。
なるべく早めに専門業者の点検・診断を受けましょう。
🔍【セルフチェックまとめ】
お家の外壁・屋根にこんな症状ありませんか?
これらの症状があるなら、塗装によるメンテナンスが必要なタイミングかもしれません。
| 症状 | 劣化のサイン | 対応目安 |
|---|---|---|
| 手に白い粉がつく | チョーキング(塗膜劣化) | 塗装の効果が切れてきた |
| 壁にヒビがある | クラック(雨水侵入のリスク) | 早期補修+塗装が必要 |
| 色があせている | 紫外線による退色 | 見た目+性能低下のサイン |
| 苔・カビがついている | 防汚性能の低下・湿気の多い環境 | 再塗装+防カビ対策 |
| 雨漏り・天井にシミがある | 防水機能の完全劣化 | 早急に点検・修繕 |
☑「うちはどうだろう?」と思ったら…
塗装が本当に必要かどうかを判断するには、実際にプロの目での診断が一番確実です。
多くの塗装業者では、無料の外壁・屋根点検サービスを行っていますので、気になる方はまず点検を受けてみるのがおすすめです。
早めの判断が、結果的に家を長持ちさせ、余計な修繕費を防ぐことにもつながります。
② どんな塗装工事をするか目的をはっきりさせよう
塗装工事と一口に言っても、「なぜ塗装をするのか」という目的によって、選ぶ塗料や工事の内容が大きく変わります。
目的を明確にすることで、業者との打ち合わせもスムーズになり、後悔のない工事につながります。
たとえば、以下のようなケースがあります。
![]() 家の見た目をきれいにしたい場合
家の見た目をきれいにしたい場合
外壁や屋根の色は、住まいの印象を大きく左右します。色選びでは周囲の景観やご家族の好みも大切ですが、汚れが目立ちにくい色や、明るさによる膨張・収縮の視覚効果なども考慮すると、仕上がりに満足しやすくなります。
![]() 雨漏りを防ぎたい場合
雨漏りを防ぎたい場合
外壁や屋根の劣化が進むと、ひび割れや隙間から雨水が侵入するリスクが高まります。 この場合は、防水性に優れた塗料を選ぶことが重要です。特に屋上やベランダの防水工事をセットで行うと、建物全体の耐久性を高められます。
![]() 長持ちする塗装にしたい場合
長持ちする塗装にしたい場合
「できるだけ塗り替えの回数を減らしたい」という方には、フッ素塗料や無機塗料といった高耐久の塗料が適しています。初期費用はやや高くなりますが、塗り替え周期を長くできるため、長期的にはコスト削減につながるケースも多いです。
![]() 夏の暑さ対策をしたい場合
夏の暑さ対策をしたい場合
近年人気が高まっているのが遮熱塗料です。 太陽光を反射して屋根や外壁の表面温度を下げ、室内の温度上昇を抑えてくれる効果があります。 エアコンの使用を減らせるため、光熱費の節約にもつながります。
このように、「見た目重視」なのか「耐久性重視」なのか、「快適さを求める」のかで、最適な塗料や工事のプランは変わってきます。
まずは「何のために塗装をするのか」を家族で話し合い、目的を明確にすることが、塗装工事を成功させる第一歩です。
③ 信頼できる塗装業者を選ぶコツ
塗装工事は、数十万円から百万円以上かかることもある大きな買い物です。だからこそ、安心して任せられる業者を選ぶことが何より大切です。業者選びに失敗すると「工事後すぐに不具合が出てしまった」「思っていた仕上がりと違った」といった後悔につながりかねません。そうならないためにも、次のポイントをしっかりチェックしましょう。
業者選びのチェックポイント
![]() 地元での実績があるか?
地元での実績があるか?
地域で長年実績を積んでいる業者は、その土地の気候や建物の特徴をよく理解しています。たとえば、滋賀なら湿気の多い気候や冬の積雪を考慮した提案ができる業者が安心です。地元に店舗やショールームを構えているかどうかも信頼性の目安になります。
![]() 訪問営業ではなく、自分で調べて連絡できるか?
訪問営業ではなく、自分で調べて連絡できるか?
突然訪問してくる営業は注意が必要です。「今すぐ工事しないと危険です!」など、不安をあおって契約を急がせるケースも少なくありません。信頼できる業者は、こちらから問い合わせをしたときに丁寧に対応してくれます。まずはインターネットや口コミで調べて、自分から連絡を取るのがおすすめです。
![]() 見積もりが詳しくてわかりやすいか?
見積もりが詳しくてわかりやすいか?
信頼できる業者は「どの部分に、どの塗料を、何回塗るのか」を明細でしっかり提示してくれます。逆に「外壁塗装一式」など大雑把な見積もりは、後で追加費用が発生するリスクがあります。見積書の内容を細かく説明してくれる業者を選びましょう。
![]() 口コミや施工事例はあるか?
口コミや施工事例はあるか?
実際に工事を依頼したお客様の声や、写真付きの施工事例は大きな判断材料になります。公式サイトやGoogleマップの口コミ、地元の評判などを参考にしましょう。できれば「施工中の様子」や「工事後のアフターサービス」についても紹介している業者が安心です。
![]() 質問に丁寧に答えてくれるか?
質問に丁寧に答えてくれるか?
こちらの疑問や不安に対して、専門用語をかみ砕いて説明してくれる業者は信頼できます。逆に「そんなの心配しなくて大丈夫ですよ」と曖昧な返事をする業者は要注意です。納得できるまで質問できる雰囲気かどうかも大事なポイントです。
 ワンポイントアドバイス
ワンポイントアドバイス
相見積もりは2〜3社に相談するのがおすすめです。
複数の見積もりを比較することで、工事内容や価格の妥当性が見えてきます。「極端に安い業者」「説明が不十分な業者」は避け、安心できる会社を選びましょう。
④ 塗料の種類と特徴を知っておこう(ざっくりでOK)
塗装工事で使用される塗料には、いくつかの種類があります。
それぞれ「耐久性」「価格」「機能」が異なり、どの塗料を選ぶかによって工事費用や塗り替え周期が変わります。
まずは代表的な塗料の種類と特徴をざっくり知っておきましょう。
| 塗料の種類 | 耐久年数の目安 | 特徴 |
|---|---|---|
| シリコン塗料 | 約10〜15年 | コストと耐久性のバランスが良く、現在もっとも人気。色や種類も豊富で選びやすい。 |
| フッ素塗料 | 約15〜20年 | 高耐久で長持ちするため、塗り替え回数を減らせる。光沢感も長持ちするのが特徴。 |
| 無機塗料 | 20年以上 | 紫外線に強く、最高クラスの耐久性を誇る。価格は高めだが、長期的に見るとコスパ◎。 |
| 遮熱塗料 | ― | 太陽光を反射して、屋根や外壁の表面温度を下げる。夏の暑さ対策・光熱費削減に効果的。 |
塗料の選び方のヒント
![]() 費用をできるだけ抑えたい
費用をできるだけ抑えたい
→ シリコン塗料がバランスよくおすすめ。
![]() できるだけ長く持たせたい
できるだけ長く持たせたい
→ フッ素や無機塗料を検討。長期的には塗り替え回数が減り、結果的にお得になる場合も。
![]() 夏の暑さが厳しい地域に住んでいる
夏の暑さが厳しい地域に住んでいる
→ 遮熱塗料を選ぶと室内の快適さがアップし、冷房費の節約にもつながる。
どの塗料がベストかは、「お住まいの環境」や「ご希望の予算」によって変わります。
たとえば、沿岸部の家は塩害に強い塗料を選んだ方がよく、交通量の多い道路沿いでは排気ガスによる汚れが目立ちにくい塗料がおすすめです。
事前にこうした基本的な知識を押さえておくと、業者から説明を受けるときも理解しやすく、納得のいく選択ができます。
⑤ 色選びは慎重に!見本だけで決めない工夫
外壁や屋根の塗料の色は、家の印象を大きく左右する大切な要素です。
色選びを失敗すると「イメージと違った」「思ったより汚れが目立つ」など、仕上がりに不満を感じてしまうこともあります。
長く住む家だからこそ、慎重に選びたいポイントです。
色選びの注意点
![]() 小さな色見本よりも、A4サイズ以上のサンプルで確認を
小さな色見本よりも、A4サイズ以上のサンプルで確認を
カタログに載っている小さな色見本だけでは、実際の仕上がりをイメージしにくいものです。
A4サイズ以上の大きなサンプルを取り寄せて、壁に当てながら確認することで、より実際に近い印象をつかめます。
![]() 日光の当たり方で色が変わるので、屋外でチェック
日光の当たり方で色が変わるので、屋外でチェック
同じ色でも、日中の直射日光・夕方の西日・曇り空などで見え方が変わります。
室内の照明だけで判断せず、必ず屋外でチェックしてみましょう。
![]() 濃い色は熱を吸収しやすく、色あせが早いことも
濃い色は熱を吸収しやすく、色あせが早いことも
黒や濃紺などの色はスタイリッシュで人気ですが、夏は熱を吸収しやすく、表面温度が高くなります。
また、紫外線による色あせも目立ちやすいため、メンテナンス周期が短くなる場合もあります。
![]() 汚れが目立ちにくい色(グレー・ベージュ系)も人気
汚れが目立ちにくい色(グレー・ベージュ系)も人気
ホワイトは清潔感があり人気ですが、汚れやコケが目立ちやすいのが難点。
その点、グレーやベージュ系の色は汚れが目立ちにくく、落ち着いた印象を与えてくれるため、多くの方に選ばれています。
シュミレーションを活用しよう
最近では、パソコンやタブレットを使って「塗装後の家の完成イメージ」をシミュレーションできる業者も増えています。実際の家の写真に色を合成して確認できるため、完成後のイメージがつかみやすく、色選びの失敗を防げます。
⑥ ご近所へのあいさつと、生活への影響も想定しよう
塗装工事は、外壁や屋根を美しく守るために欠かせないものですが、同時に「生活への影響」や「近隣への配慮」も必要になります。足場の設置や塗料のにおいなど、多少なりとも普段の生活に支障を感じる場面があるため、あらかじめ知っておくことが大切です。
工事中に考えられること
![]() 足場や養生で窓が開けづらくなる
足場や養生で窓が開けづらくなる
塗装中は、飛散防止ネットやビニールシートで建物全体が覆われます。そのため、窓やベランダが一時的に使いにくくなり、換気もしづらくなることがあります。事前に「換気のタイミング」を業者に確認しておくと安心です。
![]() 作業時間中は多少音がする
作業時間中は多少音がする
足場の設置・解体時や高圧洗浄、道具を使う作業では音が発生します。特に小さなお子様や在宅ワーク中の方は気になることもあるため、スケジュールを把握しておくとストレスを減らせます。
![]() においが気になる場合がある
においが気になる場合がある
塗料によっては独特のにおいが発生します。最近は人体や環境に配慮した水性塗料を使うケースが増えており、比較的安心ですが、それでも敏感な方や小さなお子様・ペットがいるご家庭では注意が必要です。
![]() 洗濯物は外に干せない期間がある
洗濯物は外に干せない期間がある
塗料の付着や汚れを防ぐため、塗装期間中は外干しが制限されます。工事のスケジュールを確認し、コインランドリーや室内干しの準備をしておくと安心です。
ご近所への配慮も忘れずに
多くの業者では、工事前に近隣のお宅へあいさつ回りを行い、「工事の内容」「工期」「想定される影響」などを説明してくれます。
とはいえ、施主様ご自身からも一言あいさつをしておくと、より印象が良くなりトラブル防止につながります。
「工事中はご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いします」この一言だけでも、ご近所との関係を円滑に保てます。
⑦ 契約前にチェック!見積書と工事内容をしっかり確認
塗装工事の見積書を受け取ったら、つい「金額の安さ」ばかりに目が行きがちです。
しかし、工事の品質や後々の安心感を左右するのは、金額だけではありません。
契約前にしっかり内容を確認し、納得した上で工事を依頼することが大切です。
見積もりで確認すべきポイント
![]() 塗料の種類・メーカー名は明記されているか
塗料の種類・メーカー名は明記されているか
「外壁塗装一式」としか書かれていない見積書は要注意です。どのメーカーの、どんなグレードの塗料を使うのか明記されているかを必ず確認しましょう。例えば「日本ペイントのシリコン塗料」なのか「関西ペイントのフッ素塗料」なのかで、耐久性や価格は大きく変わります。
![]() 塗る面積や回数(通常は3回塗り)が記載されているか
塗る面積や回数(通常は3回塗り)が記載されているか
塗装は「下塗り・中塗り・上塗り」の3回塗りが基本です。見積書に塗布回数や面積がきちんと記載されていない場合、手抜き工事のリスクがあります。「外壁◯㎡、3回塗り」など、具体的な数字をチェックしましょう。
![]() 足場代・養生費・清掃費なども含まれているか
足場代・養生費・清掃費なども含まれているか
塗装工事では、塗料代以外にもさまざまな費用がかかります。足場の設置・撤去費用、飛散防止ネットや養生シートの費用、工事後の清掃費などが別途請求される場合もあるため、見積書に含まれているかどうかを確認することが大切です。
![]() 保証やアフターサービスの内容は?
保証やアフターサービスの内容は?
工事完了後に「すぐに塗装が剥がれてきた」「雨漏りが発生した」というトラブルも考えられます。その際に備えて、保証期間やアフター点検の有無が明記されているかを必ず確認しましょう。保証書を発行してくれる業者なら安心です。
ワンポイントアドバイス
見積もり内容が「ざっくり」していたり、不明点が多い場合は、そのまま契約してはいけません。
曖昧な見積もりはトラブルの元です。わからないことは必ず質問し、納得してから契約することが大切です。
複数社から見積もりを取り、比較するのも安心につながります。
まとめ|塗装工事は「準備」が成功のカギ!
外壁や屋根の塗装は、見た目を美しくするだけでなく、雨風や紫外線から住まいを守る大切なメンテナンスです。
ただし、よく分からないまま契約をしてしまうと、「思っていた仕上がりと違った」「余計な費用がかかった」といった後悔につながることも少なくありません。
だからこそ、工事を始める前に次のポイントを意識して、しっかり準備しておくことが大切です。
![]() 今の家の状態をチェック … 劣化状況や塗装が必要かを確認
今の家の状態をチェック … 劣化状況や塗装が必要かを確認
![]() 目的や希望をはっきりさせる … 見た目重視?耐久性重視?暑さ対策?
目的や希望をはっきりさせる … 見た目重視?耐久性重視?暑さ対策?
![]() 信頼できる業者を選ぶ … 実績・口コミ・見積もりの明確さをチェック
信頼できる業者を選ぶ … 実績・口コミ・見積もりの明確さをチェック
![]() 塗料や色の特徴を軽く知っておく … 耐久性・機能・費用の違いを理解
塗料や色の特徴を軽く知っておく … 耐久性・機能・費用の違いを理解
![]() 工事による生活への影響も把握 … 窓・洗濯・におい・作業音など
工事による生活への影響も把握 … 窓・洗濯・におい・作業音など
![]() 見積もりや契約内容はしっかり確認… 塗料の種類・塗布回数・保証の有無までチェック
見積もりや契約内容はしっかり確認… 塗料の種類・塗布回数・保証の有無までチェック
![]() 気になることは遠慮せず相談! … 小さな疑問も事前に解決しておくことが安心につながる
気になることは遠慮せず相談! … 小さな疑問も事前に解決しておくことが安心につながる
これらを押さえておけば、塗装工事の不安がぐっと減り、納得のいく工事が実現しやすくなります。
また、ご家族と希望を話し合ったり、ご近所へ事前に声をかけておいたりすることで、工事中も安心して過ごせるはずです。
🔍 塗装工事は「ただ塗る」だけではなく、準備と確認で成功が決まります。
迷ったときは、まずは無料相談や現地調査を利用して、プロの意見を聞いてみましょう。
お住まいの状況に合わせて、最適なプランを提案してもらえるはずです。