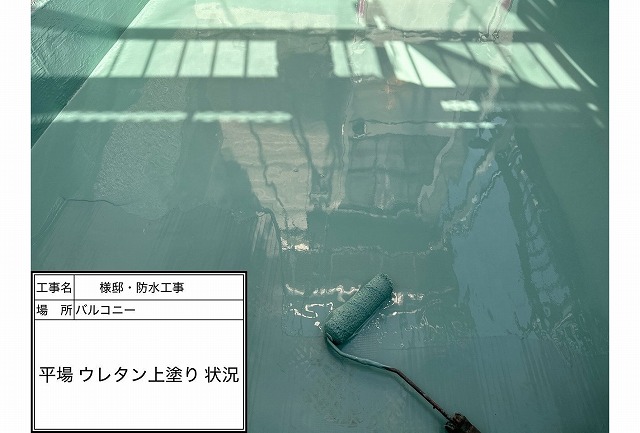外壁塗装は何回までできる? 考え方や時期を解説 l塗り達
2023年3月31日 公開
初めて外壁塗装を検討中の方も、昔一回やったことあるよという方も、外壁塗装は何回目までできるか知っていますか?
住宅の寿命は、木造住宅でおよそ30年、鉄骨住宅で30年~50年 ほどといわれています。
使い方やメンテナンスによっては、もっと長持ちする場合もありますが、
住宅の寿命が尽きるまでに外壁塗装は何回までならできるのでしょうか?
今回の記事では、外壁塗装ができる回数や、注意点を解説していきます。
外壁塗装のサイクル
外壁塗装は、一般的におよそ10年~15年で一度といわれます。
この年数の根拠は、塗膜の耐久性です。

たとえば、新築の場合は基礎や躯体から一度に作るため高額な費用が掛かります。
そのため、外壁の仕上げには安価で耐久性があまり高くない塗料が使われることが多いのです。
塗り達で取り扱っている一番リーズナブルな塗料は、シリコン塗料で、期待耐久性はだいたい8年~10年くらいです。
シリコンよりさらにグレードの低い塗料にはアクリル系塗料がありますが、こちらは対候年数ももう少し短くなるイメージです。
新築後に外壁塗装をする時期は10年~15年といわれますが、実際には使われている塗料の耐久性によって異なりますので、フッ素や無機塗料を使っている場合は、塗り替え時期ももっと後になります。
具体的に塗り替えの時期と築後年数を考えてみましょう。
だいたい10年くらいもつシリコン塗料で塗装を行う場合は、
・新築後10年で塗り替え (1回目) ■10年経過で1回目完了
・塗り替え後、さらに10年で塗り替え(2回目)■20年経過で2回目完了
・さらに10年後に塗り替え(3回目)■30年経過で3回目完了(次回は40年目?)
単純に10年おきに塗装を行うと考えると、このようなサイクルになってきます。
外壁塗装は何回まで行う?
木造住宅の場合、およそ30年が寿命といわれています。30年目以降は外壁だけではなく躯体の劣化も出てくるため
大きなリフォームをしたり、建て替えを行ったりするなど、塗装以外のメンテナンス方法を検討することも出てきます。
そのため、
建物の寿命
塗膜の耐久性
ご家族のライフプラン
によって、何回まで塗装するかは変わってくるということになります。
しかし、この考え方はあくまで、家の寿命が来るまでに何回塗装を行うかという話であり、
実際に、何回までは塗装でメンテナンスができるのか?という問題とは少し違ってきます。
外壁塗装によるメンテナンスは、何回までできるのか?
メンテナンスで外壁塗装を行う際に、気を付けなくてはいけないことの1つに、
いま現在はどんな塗料で塗られているのか
ということがあります。
外壁塗装に使う塗料は、下地に密着することで塗膜を作り、その効果を発揮します。
しかし、下地や現在塗ってある塗料との相性が悪い場合、うまく密着せずにすぐ剥がれてきてしまうことがあるのです。
そのため、初めての外壁塗装ではなく、
過去に1度(もしくは2度)外壁塗装を行ったことがある場合のメンテナンスは、非常に気を付けて外壁を見ることが必要になります。
外壁塗装を複数回行う場合、
「下地の上の、1回目の塗膜の上の、2回目の塗膜の上に、今回(3回目)塗る塗料」 を考えることになり、ここで選択を間違えてしまうと施工不良になることがあるためです。

結論を言えば、外壁塗装は何回でも行うことができます。
ただし、きちんと現在の状況を見極めて、使う塗料や工程を考える必要があるため、
回数が増えるほど大変で、費用も掛かりやすくなるということです。
また、塗膜で守られているとはいえ、やはり外壁材の劣化も進んでいきます。
塗装では補修ができない欠けや割れ、激しい劣化などが見らる場合は、塗装ではなく外壁材の張替えなどを行った方が、結果的に家が長持ちすることもあるため、何回でも塗装でよいということはなく、その時の状況に応じて最善の策をとる必要があるでしょう。
2回目以降の塗り替えもおまかせください
塗り達では、現場をたくさん見てきた施工担当者、現場経験の多い職人が数多く在籍し、築年数が古い住宅の塗装も数多く行ってきました。
実際に、他社では断られたというお客様もいらっしゃいましたが、最善の方法をご提案しご評価いただいています。
外壁塗装が初めての方も、2回目3回目という方も、ぜひ一度塗り達にご相談ください!
ご家族のライフプランに合わせた最適なプランをご提案いたします。