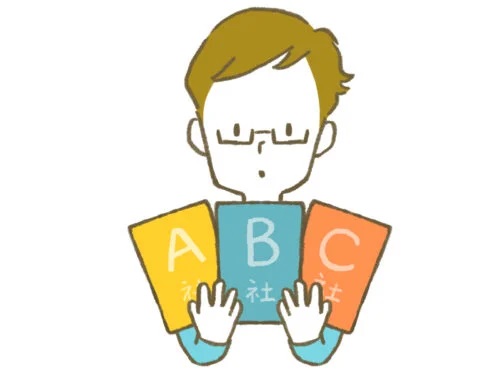2024年2月9日 更新!
屋上の防水工事費用は修繕費にできる?判断のポイントについて l塗り達
2024年2月9日 公開 マンションやアパートで屋上がある場合や、戸建て住宅でも屋上を設けているケースがあります。 屋上は、屋根がない代わりに防水施工をすることがほとんどです。防水層が劣化すると、雨漏りにつながりますのでメンテナンスは必須です。 本記事では、屋上防水工事について修繕費にできるのか?について解説しています。ご参考になさってください。 屋上防水とは 屋上防水とは、建物の屋上に防水工事を行う工事の事です。 防水工事は、次の通り「水を防ぐ」工事です。屋外にあるため、雨水の侵入を防ぎ雨漏りしないようにすることが最大の目的です。 防水工事には下記のようにいろいろな施工方法があります。 ウレタン防水 液状のウレタンを硬化させて防水層を作る方法です。液体を使って塗っていくのでシームレスな防水層を作れます。 シート防水 あらかじめ作られた防水性のあるシートを使って防水層を作ります。人の手で防水層を作るわけではないので、均一で強固な防水層が作れます。 FRP防水 戸建て住宅でよく用いられる方法で、繊維強化ガラスを使って防水層を作ります。大半の下地に施工でき、耐久性も高いコスパのよい方法です。 アスファルト防水 最古の防水工事方法として知られるアスファルトを使った防水工事です。耐久性が非常に高くマンションなどの屋上はほぼアスファルト防水ですが、費用も高額です。 防水工事を行うタイミング 防水工事は、基本的に建物を新築するタイミングでまず行います。 しかしいずれの方法で工事をしても、紫外線などによる劣化は避けられないため、7~15年ほどでメンテナンスが必要になります。 雨漏りを防ぐことが目的なので、できれば雨漏りが起こる前にメンテナンスを行うことが望ましいですが、中には防水層がほぼ機能しなくなってから施工するケースや、元々は防水施工をしていなかった場所に工事を行うケースもあります。 雨漏りが起こってしまうと、屋上だけの問題ではなく躯体の強度に影響が出るため、各施工方法の耐久年数と、劣化状況を見ながら早めにメンテナンスを行うほうがよいでしょう。 屋上防水が修繕費になるケース 屋上防水が修繕費になるかどうかは、次の条件を確認する必要があります。 ・その工事をすることによって、建物の寿命が延びる、耐久年数が延長されるかどうか 防水工事を行う目的は、工事行うタイミングで触れたように、劣化した分のメンテナンスを行って元の状態に戻すことが最低限の目的です。 しかし、中には工事を行ったことによって、劣化前の状態より建物の価値が上がる(建物の寿命が延びたり、耐久年数が延長されたりするような工事)もあります。 修繕費とするためには、工事によって元々の価値より高くならないようにする必要があります。 防水工事の結果、建物の価値が上がる場合は「資本的支出」となり、修繕費にはできませんので注意しましょう。 防水工事前に施工店へ相談しましょう 防水工事を行う場合には、施工方法によっては建物の価値が上がることもあります。 しかし修繕費にしたい場合はこれは避けなければいけません。 防水工事の業者は、お客様にとっての最善を考えるため、長持ちする耐久性の高い方法をすすめてくるはずです。 建物のためにはその方がよいと考えられますが、修繕費にしたい場合は施工前に相談するようにしましょう。MORE