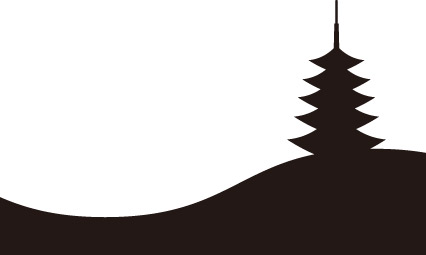まもなく開催
まもなく開催 2026年1月15日 更新!
🎊🎊いよいよ本日 初日を迎えます!! ”初売り祭” 6日間限定🎊🎊
2026.1月16日公開 新年あけましておめでとうございます 旧年中は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございました 本年もどうぞよろしくお願いいたします 2026年も皆さまのお住まいづくりを全力でサポートいたします 早速ですが塗装をお考えの皆様にお得な情報がございます。最後までお付き合いよろしくお願いいたします。 6日間限りの特別イベント 初売り祭 京都市、宇治市、八幡市、草津市、守山市、栗東市、野洲市、大津市に地域密着の 外壁塗装・屋根・雨漏り専門店「塗り達」では、地域の皆様限定の初売り祭を開催いたします! 【期間】残り3日間です! 2026年 1月16日(金)17日(土)18日(日) 終了 23日(金)24日(土)25日(日) 日にち限定のイベントになります。お日にちにご注意していただき、この機会にどうぞよろしくお願いいたします! 【場所】各店舗とも駐車場を完備しております!! 本店(淀ショールーム) 京都市伏見区淀際目町226-2 9:00~18:00 駐車場完備 伏見店 (深草ショールーム) 京都市伏見区深草谷口町55-1 9:00~18:00 駐車場完備 滋賀店 (草津ショールーム) 滋賀県草津市野村6丁目3-19 9:00~18:00 駐車場完備 【特典内容】✅豪華14大特典ご用意!! Wご来場特典(アンケートへのご協力をお願いします) ①選べる日用品 ②(お子様特典)お菓子つかみ取り 2,000円分 5種類から選べる 御見積特典(御見積依頼の方) ①スターバックスギフト券 ②Amazonギフト券 ③JCBギフト券 ④ハーゲンダッツギフト券 ⑤総合カタログギフト 30,000円分 5種類から選べる ご成約特典(ご成約の方・ご契約金額100万円以上の方限定) ①窓・サッシ洗い工事 ②和牛カタログギフト ③Amazonギフト券 ④グルメカタログギフト ⑤JCBギフト券 お正月特別特典 おみくじ抽選会(お年玉との併用不可・ご契約金額100万円以上の方限定) 超大吉 25万円OFF 大吉 10万OFF 中吉 5万円OFF 小吉 1万円OFF お年玉(おみくじ抽選会との併用不可・ご契約金額100万円以上の方限定) 足場代 無料!!(3棟限定) チラシ 塗り達 表面 チラシ 塗り達 裏面 【最後に・・・】 外壁塗装・屋根塗装(工事)は本来、まとまった費用がかかる工事。 だからこそ、この イベントの特典はとてもオトク! 塗装やお家のリフォームをお考えの皆様、この機会にお越しいただきますと大変お得ですよ!! ご予約いただけますとスムーズにご案内することが可能です。 もちろんフラッとお気軽にショールームに話を聞くだけでも 塗料を見るだけでも 2026年 1月16日(金)17日(土)18日(日) 残り3日間です! 23日(金)24日(土)25日(日) 各店舗9:00~18:00 0120-503-439 WEBお問合せ 👉 この機会を逃さず、オトクに外壁・屋根リフォームをご検討してみてください!お待ちしております!!MORE