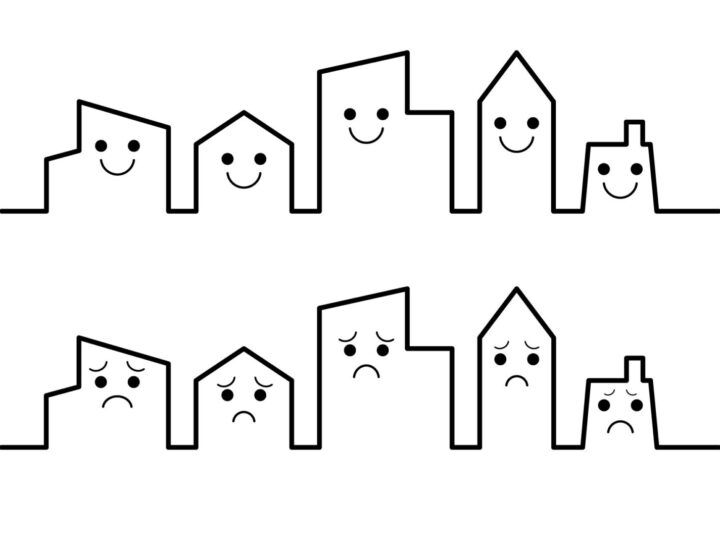2024年5月26日 更新!
城陽市にて 外壁塗装・屋根塗装のお問合せ
皆さんこんにちは! 塗り達の営業担当の藤井です♪ 本日は、外壁と屋根の劣化でお問合せいただきました。 劣化状況から提案内容をご紹介したいと思います。 外壁の劣化状況① 築16年の窯業サイディングですが、日光の当たらない所にはコケが発生している状態でした。 また外壁の間のシーリングと呼ばれる目地も黒くなってきているのがわかります。 また、サイディングボードは四つ角をビスで止めているのですがその部分からひび割れが発生してしまう事がよくあります。 これは、10年程経つと外壁と外壁の間の目地部分の緩衝剤の役割があるシーリングが硬く劣化しお家が何らかの振動に追随できなくなり引き起こす事がほとんどです。 状態がひどくなると、サイディングボード自体が剥がれ落ち、ボードを貼替えることになります。 その前にひび割れしている所はシールでしっかり埋め、塗装で塗膜もつき綺麗に仕上がります。 屋根の劣化状況② 続いて屋根の劣化状況になります。 屋根の種類はカラーベストで所々色褪せが目立ちました この屋根が後10年程すると、割れが発生したり屋根材の中が痛みイメージでいうとお菓子のウエハースのような中に隙間が空いてバリバリとした状態になります。 ここのお家は、築11年で塗り替えの依頼を頂いている状態なので遮熱性の高い塗料でご提案させて頂きます。 外壁の間に目地と呼ばれる緩衝剤の役割がある 塗り達では外壁診断と見積・施工提案を無料で行っております。 塗装工事をご検討の方は塗り達までご相談ください!MORE