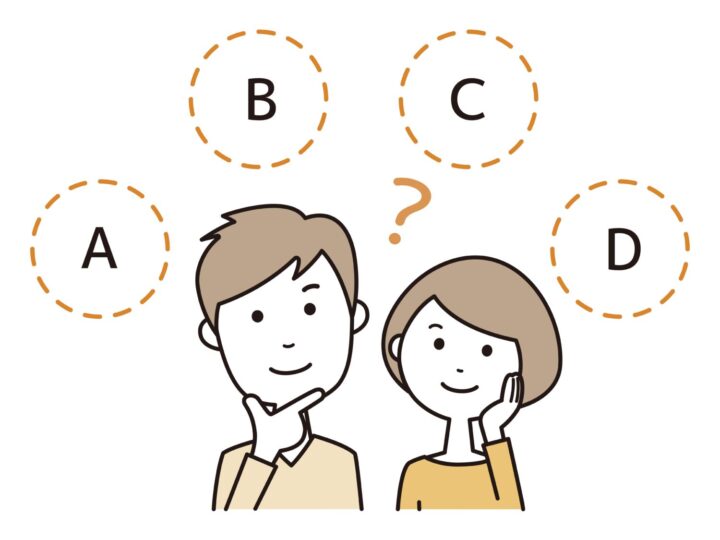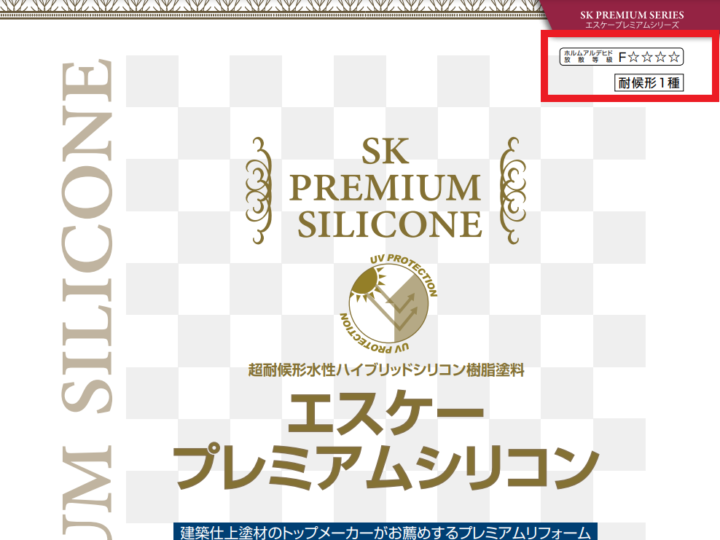2024年1月6日 更新!
アステックペイントとは?人気の遮熱塗料や耐用年数について l塗り達
2024年1月6日 公開 この記事では、アステックペイントについて解説しています。 アステックペイントは福岡県に本社を置く日本の塗料メーカーです。 戸建て住宅やマンションから工場の塗装に使えるものまで、建築塗料を幅広く開発しています。創業は2000年10月と比較的新しい会社ですね。 施工品質が優れた施工店にのみ塗料を販売している「直販体制」を取っており超低汚染リファインシリーズをはじめ様々な塗料を開発・製造販売しています。 アステックペイント 公式サイト アステックペイントの特徴 アステックペイントの特徴を解説します。 直販体制 先述のように、施工店へ直接販売する「直販体制」をとっています。 一般的な塗料メーカーは、メーカーと施工店の間に問屋や販売店が存在し、中間マージンがかかります。 アステックペイントでは直販体制によってこの中間マージンをなくし、塗料の仕様や施工上の疑問などにも担当者と直接話ができるため、フォロー体制も整っているといえるでしょう。 施工店は現場で知識や技術を身に付けていますが、状況によって塗料メーカーに確認したり、もっとよい施工方法はないかと相談することもあります。そのような時メーカーに直接確認ができるアステックペイントは心強い味方ですよね。 塗料を購入できるWEBサイトあり アステックペイントに加入・加盟している方を対象に塗料が購入できる「AP ONLINE」もあります。 塗料の販売だけではなく、知識が増えるコラムや製品の詳しい情報なども掲載あり、ボリュームのあるサイトです。 アステックペイントの塗料 アステックペイントの主力商品は超低汚染リファインシリーズです。 (出典:アステックペイント 公式サイト) 外壁用・屋根用とそれぞれあり、無機塗料に分類されます。 また遮熱効果もあり、耐久性をアップさせています。 無機成分の細かい粒子で、緻密な塗膜を作り上げ、外部からの汚れの付着を軽減します。 (出典:アステックペイント 公式サイト) くわしくはこちら(外部リンク) つや消しタイプでも、期待耐用年数は17~20年と高耐久をうたっています。 塗料メーカーでは、発売前に様々な実験や検証を繰り返し、耐久性や性能について研究を重ねています。 有名塗料メーカーを使うと安心とされるのは、開発に時間とお金をかけ、実際に使われている建物での実績を積み上げているからなんですね。MORE