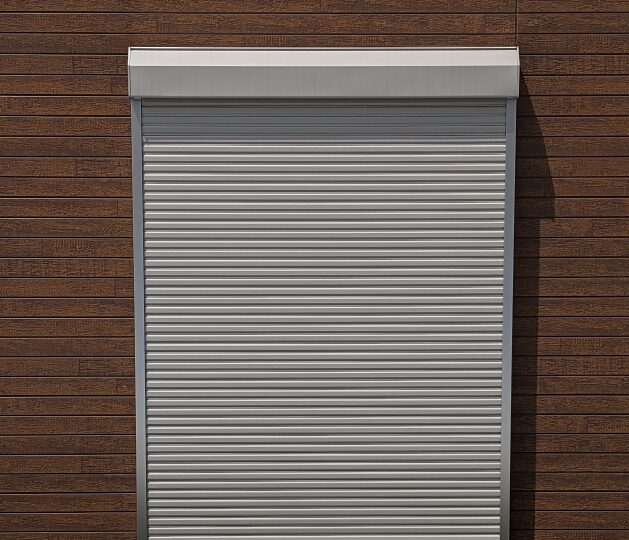2023年8月25日 更新!
矢切ってなに?特徴や外壁塗装との関係を解説 l塗り達
2023年8月25日 公開 この記事では 矢切について解説しています。 矢切(やぎり)は、外壁と屋根の間の三角形のスペースのことをいいます。 部材の名前ではありません。 切妻屋根や入母屋屋根の場合、屋根が三角形になる部分があり、その部分を指します。 #gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 50%; } #gallery-1 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-1 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */ 矢切部分は、すぐ上に屋根があり雨がかかりにくいため、換気のための通風孔を設けている場合もあります。 屋根内部の湿気を逃がすことができ、2003年より建築基準法で定められている24時間換気システムの1つとして機能します。 改正建築基準法について 詳しくはこちらを参照ください。 改正建築基準法 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/sickhouse.files/sickhouse_1.pdf 塗装の際は、同じ色で仕上げることもできますが、ワンポイントで色を変えたり、サッシの色に合わせることも可能です。MORE