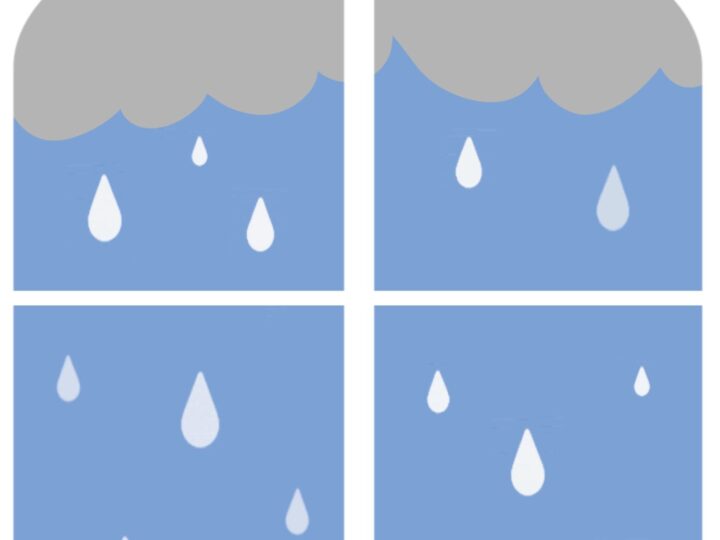2024年12月24日 更新!
外壁塗装の剥がれの原因とは?補修方法についても解説 l塗り達
2024年12月24日 公開 外壁の一部や全体にはがれが見られることがあります。 一部分だけはがれている場合は、なぜここだけこんなにはがれるの?と疑問に思ってしまうでしょう。 今回は外壁の剥がれについて原因や補修方法を解説します。 外壁の剥がれの原因 外壁の剥がれは、表面の塗膜のはがれであることがほとんどです。 塗膜は本来外壁にしっかりと密着しています。 しかし、 経年劣化 雨漏り 施工不良 等の原因ではがれが生じることがあります。 経年劣化 時間の経過とともに塗膜の耐久性を過ぎ、塗膜のはがれが見られるケースです。 特に何をしたわけでもないのにはがれが見られる場合は、そろそろメンテナンスのサインです。 雨漏り 外壁から雨漏りが発生すると、よく見られる症状の1つが塗膜のはがれです。 内側に水が回って、ぺりぺりとはがれてきてしまいます。 サッシ廻りや笠木の下など一部分だけはがれている、雨漏りのほかの症状がみられるなどの場合は雨漏りによる剥がれが疑われます。 施工不良 下塗りを行っていない、塗料の撹拌や希釈が適切でないなど、正しく施工されていなかった場合に起こる剥がれです。 施工不良の場合、耐久年数を待たず数年ではがれてきてしまうことが特徴です。 外壁の剥がれの補修方法 外壁のはがれが見られたら、塗装を含めた補修工事を行います。 まず外壁のはがれている部分を丁寧に取り除きます。はがれの上から塗装をしても密着せず同じようにはがれてきてしまうからです。 さらに凹凸面を埋めるために左官工事を行います。この施工事例では、モルタル外壁の剥がれをセメントパテを使って埋め平らにしています。 下地をきれいにし、左官で埋めたあと、下塗りと上塗りを工程遵守で行います。 剥がれを残したまま塗装しても凹凸の跡が残ったり、新たにはがれることがあるため、下地処理をしっかりと行うことが大切です。 雨漏りしている場合 雨漏りが原因ではがれが見られる場合は、まず雨漏り補修を行います。 雨漏りは勝手には直らないため、補修を行ってから外壁の塗装を行います。 外壁のはがれに気づいたら、まずは調査を依頼しましょう 外壁の剥がれについて解説しました。 一口に剥がれといっても原因は様々です。外壁の補修前に原因となる要素を直して、新たな剥がれを防止しましょう。 ↓↓外壁の剥がれについてお問い合わせはこちら↓↓MORE