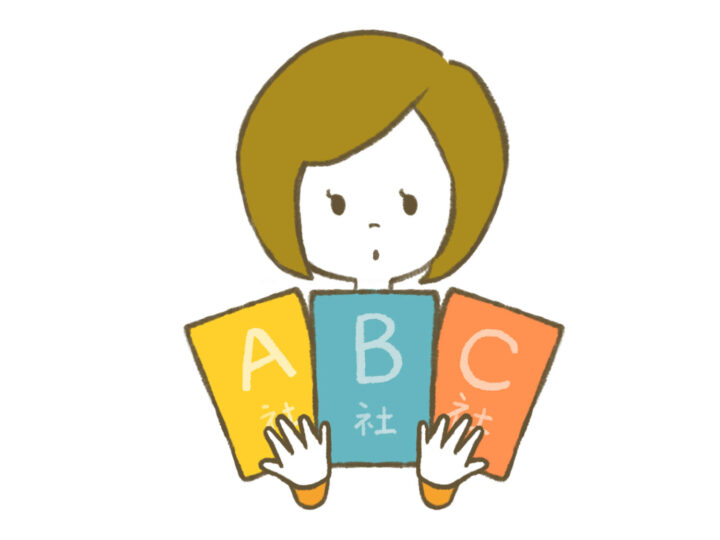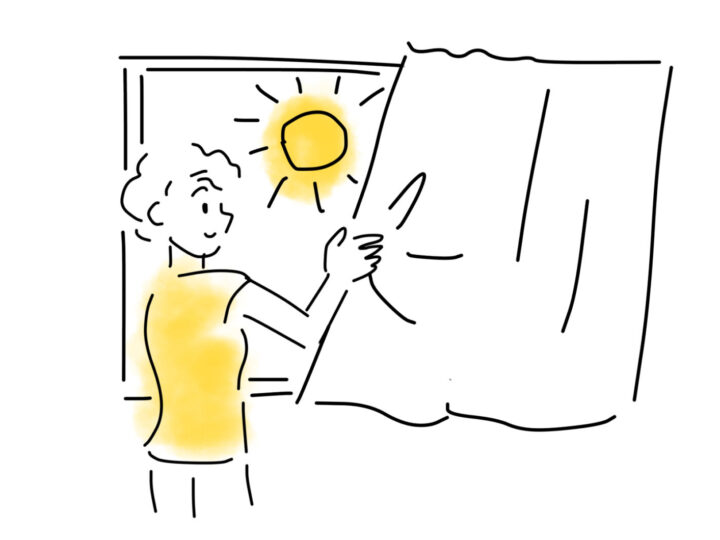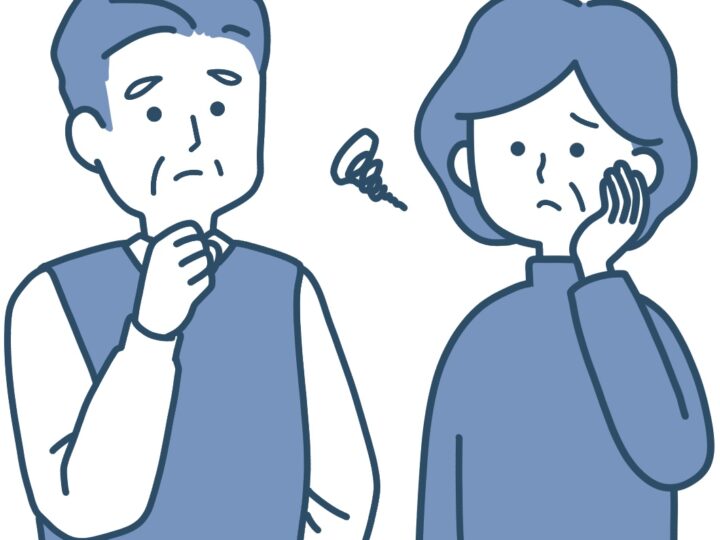
2023年10月6日 更新!
したくてもできない!?外壁塗装工事ができない家とは?
2023年10月6日 公開 外壁塗装は、外壁やお家を守るメンテナンスとして、とても有効な方法です。 しかし、中には塗装工事ができないケースもあります。 本日は、外壁塗装がしたくてもできない事例をご紹介します。 外壁塗装の必要性 外壁塗装は、塗膜で外壁材を守り、ひいてはお家全体を守るために行うメンテナンス方法です。 外壁は、約10年で塗り替えが必要です。 経年劣化で次のような症状が見られたら塗装のサインです。 チョーキング 塗膜が劣化し粉状になる症状です。表面にとどまってはいるものの密着しておらず塗膜が劣化している状態です。 手で触るとチョークの粉のように白くつくことから、「チョーキング」と呼ばれます。 塗膜のはがれ 塗膜のはがれは、雨漏りのサインである場合もあります。外壁材と塗膜の間に水分が入り込み、内側からはがれてくる症状です。 カビ・コケ カビやコケは、水分を好みます。北側の外壁など日光が当たりにくい場所に生えやすいですが、外壁が水を吸って湿っているために起こる現象でもあります。 塗膜が元気であれば水分をはじいて吸い込むことはないので、劣化症状の1つとして覚えておきましょう。 シーリングの劣化 特にサイディングやALCの外壁材の場合、つなぎ目の部分にシール処理をしてあります。隙間から水が入り込まないようにするためと、緩衝材の役割があります。 シーリングはゴムと同じような性質なので、経年劣化で切れたりはがれたりしてきます。 外壁の内側に水が入り込む原因となるので早急にメンテナンスが必要です。 色褪せ サッシ廻りなど部分的に色褪せしている場合も、塗膜の劣化症状が疑われます。 塗膜は均一な厚みを保って外壁材を守っていますが、一部の塗膜が薄くなってくると、一気に周りの塗膜も弱ってきます。 外壁塗装ができないケース 外壁や約10年ほどで上記の劣化症状がみられるようになります。 通常、外壁塗装工事を行えば、補修+美観アップでメンテナンスができるのですが、次のようなケースの場合は塗装工事がしたくてもできないことがあります。 劣化が進行しすぎている 劣化症状を放置し続けていると、塗膜だけではなく外壁材そのものが損傷してきます。 外壁塗装は、古くなった塗膜を新しくし引き続き外壁材を守ることができますが、劣化が進行しすぎると塗装ではメンテナンスができないケースもあります。 塗装ができない素材である 外壁塗装は、外壁だけではなく付帯部や外構などの塗装も含まれることがあります。 基本的にアルミは塗装ができないため、アルミでできたサッシなどは塗装工事ができません。 雨漏りがひどく、外壁材や躯体が損傷している 劣化症状、特にシーリングの劣化などを放置しているうちに雨漏りが発生しているケースがあります。 内部に入り込んだ水は、内側から外壁を損傷させたり、躯体を腐食させたり、シロアリの餌食になってしまうこともあります。 日本の家屋が木造住宅が多いので、雨漏りは躯体の強度にかかわる天敵ともいえます。 劣化症状は見た目だけの問題ではなく、躯体に影響を与えるため、傷みすぎた住宅の場合塗装ではメンテナンスしきれないケースもあります。 早めの塗装工事でお家を長持ちさせましょう 塗装工事ができない事例について解説しました。 劣化症状を見た目がすこしよくないだけと放置せず、早めのメンテナンスを心掛ければ、大切なお家に長く住まうことができます。 塗装工事ができないケースの場合は、外壁材の場合カバー工法や張替、屋根の場合は屋根工事などを検討することになるため、塗装工事よりもメンテナンス費用が高額になりやすくなっています。 新築からおよそ10年経っていれば、一度劣化症状を診断してもらいましょう。MORE