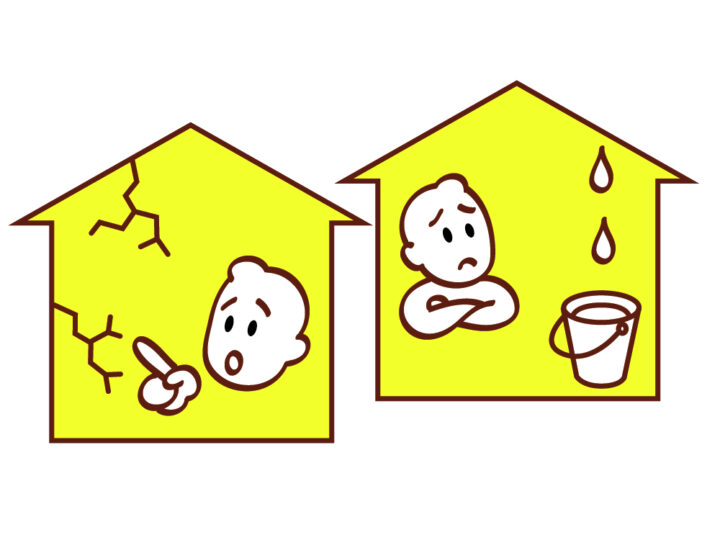2023年9月29日 更新!
シート防水とは? 特徴やメリットを解説 l塗り達
2023年9月29日 公開 この記事では、シート防水について解説しています。 シート防水は、防水工事の施工方法の1つで、防水性のあるシートを用いて防水層とし、下地に雨が入り込むのを遮断する工事です。 防水層として使われるシートの材質は ・塩ビシート ・合成ゴム 等があります。 シート防水の特徴とメリット・デメリット シート防水はあらかじめ製造された防水シートを持ち込んで、現場で張り合わせていく防水工事です。 そのため、塗膜防水のように現場で防水層を作ることがなく、防水層は一定の厚さに保たれた状態で施工できます。 広くて平らな面への施工を得意とし、屋上や広めのルーフバルコニーなどで採用されています。 メリット ・防水層の厚さが均一にでき、防水性が高い ・そんな下地にでも施工できる(下地を選ばない) ・工期が短い デメリット ・施工費用が高い ・1か所の穴や損傷が全体の防水性に大きく影響する ・複雑な形状の場所には施工しにくい 密着工法と機械固定法 シート防水には、シートの固定の仕方に2つの工法があります。 密着工法 密着工法は、専用の接着剤を用いて下地に密着させてしまう方法です。 接着剤とシートだけで施工できるので、比較的狭い場所でも施工ができます。 機械固定法 機械固定法は、固定ディスクを使って専用の機械で固定する方法です。 #gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-1 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-1 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */ この方法は、密着工法とは違い下地に完全には密着しません。 そのため、すでに雨漏りしている場合など、下地に水分が含まれている場所でも施工が可能です。 密着工法で雨漏り箇所に施工をしてしまうと、下から上がってきた水分が蒸発できず膨れ等の原因となります。 機械固定法の場合は、密着しておらず下地とシートの間に通気の取れる緩衝シートを挟み蒸発してくる水分をうまく逃がすことができるのです。 いずれの場合もシートとシートの隙間は液状シールで埋め、シート同士が完全にくっついた状態に仕上げます。 シート防水のメンテナンス シート防水は、シートの経年劣化により防水性が失われるため、メンテナンスが必要です。 ・塩ビシート:10~20年 ・合成ゴムシート:10~15年 が耐用年数といわれています。 また、シート自体が大丈夫であってもシートのめくれや立ち上がり部分の剥がれなどが原因で、シートの下に雨が入り込んでしまうこともがあります。 膨れ等がある場合は防水層が機能していない可能性があるので、耐用年数を待たずにメンテナンスを行いましょう。MORE