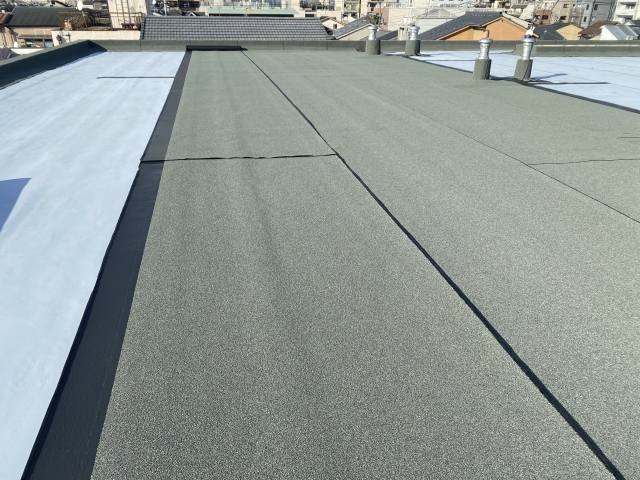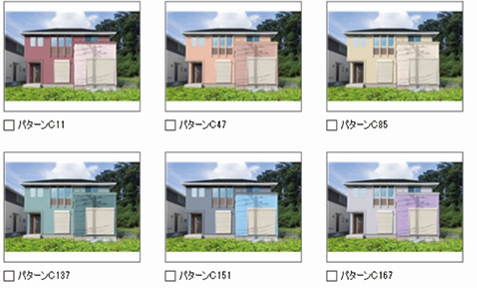2023年7月1日 更新!
外壁塗装は目地のメンテナンスもご一緒に! l塗り達
2023年7月1日 公開 この記事では目地について解説しています。 外壁における目地とは、サイディングボードやALCのつなぎ目の部分のことを言います。 現在の日本の戸建て住宅は、木造住宅が主流です。 外壁の仕上げには乾式工法・湿式工法とよばれる2種類があり、サイディングボードやALCパネルを使う方は乾式工法と呼ばれます。工場で生産されたパネルを持ち込んで外壁にはめていきます。 湿式工法とは、モルタルなど現場で作り仕上げる外壁のことを言います。 目地の役割 乾式工法における目地の役割は緩衝材としての働きです。 前述のサイディングボードやALCパネルは、すでに工場で出来上がった板状のものを現場に運び入れて外壁として使います。一枚ものでは貼れないため、何枚も組み合わせて使います。 サイディングボードもALCもそれ自体に耐久性があり固いため、ボードとボードの隙間になにも入れていないと地震の衝撃やゆがみでボード自体が衝突し欠けや割れの原因になってしまうのです。 そこで、わざとボード同士に隙間を作り、その隙間をシーリング材で埋めています。これが目地です。 シーリング材はゴムのような材質で弾力性があります。 そのため、ボードの何らかの衝撃が加わっても目地のシーリング材が緩衝材となってボード同士の衝突を防いでくれるのです。 目地にシーリングを使う理由 では、緩衝材にシーリング材が使われている理由は何でしょうか。 1つは、伸び縮と適度な弾力があるので、緩衝材として衝撃を吸収しやすいからです。 そしてもう1つは、ゴムの性質を生かし目地にピッタリと収まるため、隙間ができない=雨が入らないからです。 外壁は住宅の一番外側で、その下には防水シートや断熱材、躯体が隠れています。 ボードの隙間が埋まっていないと、目地から内側に入り込んで雨漏りの原因となるのです。 外壁塗装と目地のメンテナンスを一緒に行った方がよい理由 シーリング材はゴムのような性質だと説明しました。 ゴムと同じようによく伸びよく縮ますが、劣化すると同じようにぷちっと断裂します。 外壁塗装の際には、塗膜を新しくするため外壁材自体の耐久性はアップします。 しかし、外壁に新しい塗膜が乗っていても、目地のシーリングが劣化していると、その隙間から雨が入り込み結果的に雨漏りを招いてしまいます。 水が内側に入り込むと、雨漏りで塗膜がはがれてくる症状が見られます。 そのため、せっかく外壁塗装をしたのに、耐久性が思っていたよりなかった という結果になってしまいます。 外壁塗装の際には、目地がある場合はシーリングのメンテナンスも一緒に行うことが必須です。 シーリングのメンテナンスをしない場合は、外壁塗装の保証もできないという業者もいますので、必要なメンテナンスと認識しておきましょう。 目地のシーリングの耐用年数 新築の住宅の目地に使われるシーリング材は、耐久性はおよそ10年といわれます。 これは、使用しているシーリング材の種類にもよりますので一概には言えませんが、基礎や躯体にお金がかかる新築の場合シーリングは比較的安価なものを使うことが多いようです。 目地のメンテナンスの際は 外壁塗装と一緒にメンテナンスを行うことが大切ですので、外壁と目地のシーリング材の耐久性はおよそ同じくらいのものを選ぶ方がよいでしょう。 外壁塗装の塗料では、フッ素や無機などは耐久性が高く15年以上もつものもあります。 塗り替えの際には、塗装の耐久年数に合わせて、耐久年数のたかいシーリング材を選択すれば、次回のお手入れもどちらも無駄にならず同じ時期にできます。 外壁よりも劣化が進んでいたらまずは現地調査を 外壁も目地も同じように劣化していきますが、明らかに目地だけ劣化が進行している、はがれている、ちぎれている等の場合、施工不良も考えられます。放置していると雨漏りの原因になり、まだまだ使える外壁も痛めてしまうことになるため、まずは目地の劣化診断を依頼しましょう。 原因がわかって必要があれば、目地だけ新しくすることもできます。 まずは無料の劣化診断をお試しくださいMORE