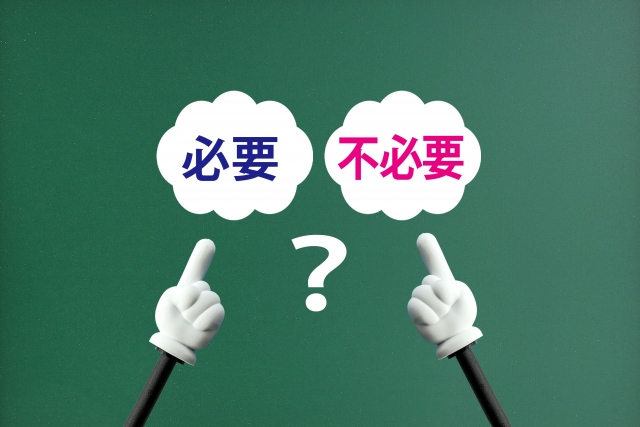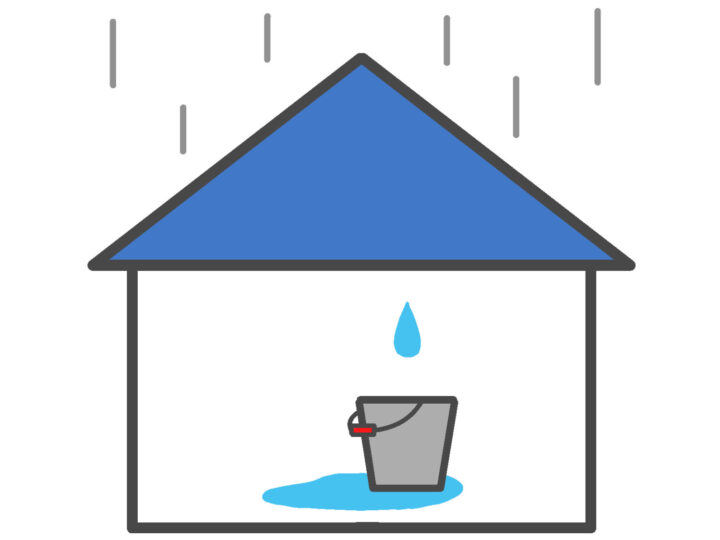2023年11月16日 更新!
外壁塗装のグラデーションとは?1色塗りとは違う多彩なデザインで人気! l塗り達
2023年11月16日 公開 サイディングボードのデザインには、レンガ調やタイルのようなものなどいろいろなバリエーションがあります。 1棟すべておなじデザインにせず、部分的に柄ものを取り入れているお家もあり、おしゃれで個性的ですよね。 そんなこだわりの外観を、塗装工事を行ってもそのまま維持できる、または新たに模様を付けることができるのをご存知ですか? 多彩工法 グラデーション塗装などと呼ばれるこの方法、塗り達では「多彩工法」を行っています。 こちらの写真は、 上部:多彩工法 下部:1色のベタ塗り で仕上げたサンプルです。 同じサイディングとは思えないほど立体感と高級がありますよね。 認定施工店のみ施工可能 多彩工法は、スズカファイン株式会社の認定施工店でしか施工することができない特殊な工法で、京都でもできるところはとても少ない工法です。 塗り達は、「多彩工法の認定施工店」として、施工することが可能です。 多彩工法の施工事例 多彩工法で仕上げると、まるで外壁を貼り換えたかのように印象がガラッと変わり、明るくしかも高級感のある仕上がりになります。 #gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 50%; } #gallery-1 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-1 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */ 施工前 #gallery-2 { margin: auto; } #gallery-2 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 50%; } #gallery-2 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-2 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */ 多彩工法のカラーバリエーション 多彩工法は、2色または3色のデザインからお選びいただくことができ、イメージ合わせてカラーシミュレーションも可能です。 ▲2色仕上げ ▲3色仕上げ (出典:スズカファイン株式会社 WB多彩仕上工法 カタログ) 注意点 多彩工法は、サイディングの凸凹面を生かして多色をのせる方法です。 そのため、凹凸がはっきりとある外壁のほうが効果が出やすくなっています。 窯業系サイディングボード専用の工法のため、 金属サイディングやモルタル、ALCへの施工はできません。 多彩工法なら塗り達へ! グラデーション塗装とも呼ばれる「多彩工法」についてご紹介しました。 いま一色塗りの外壁も、凹凸のあるサイディングボードなら多彩工法で施工が可能です! 京都市内に2店舗ある塗り達のショールームでは、多彩工法のサンプルを展示しているほか、カラーシミュレーションで多彩工法のシミュレーションも可能です。 耐久性とデザイン両方を兼ね備えた多彩工法なら、ぜひ塗り達にご用命ください!MORE