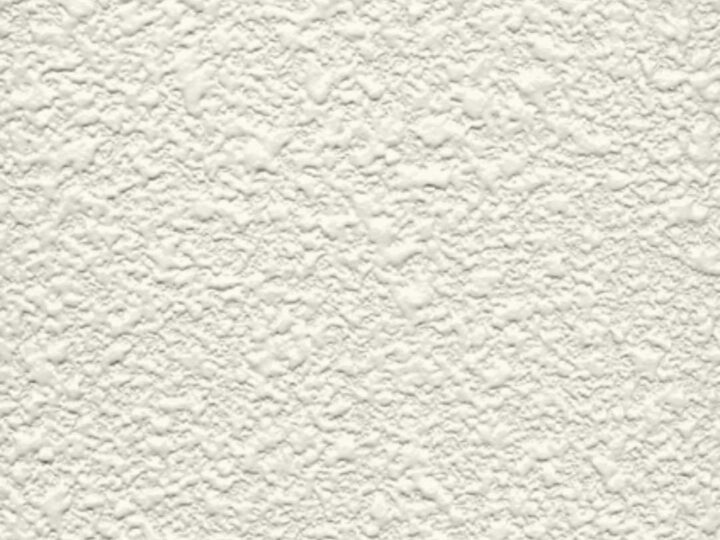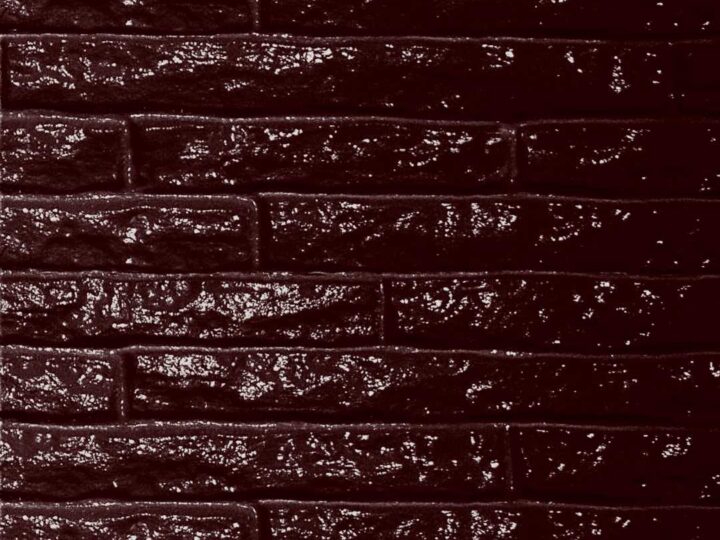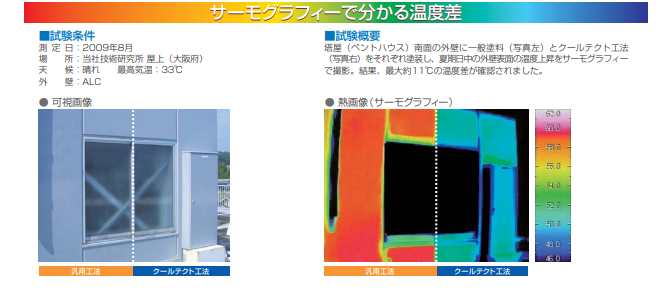2023年4月4日 更新!
外壁塗装のパターンとは? いろいろな種類から好みの仕上がりに l塗り達
2023年4月4日 公開 外壁塗装は、ただ塗るだけではありません! ご希望によっては、パターン(模様)を付けることも可能です。 この記事では、外壁塗装のパターンについて解説していきます。 外壁のパターン(模様)とは 外壁のパターンを考えるときに、まず外壁材の種類について、代表的なもの2つをおさらいしておきましょう。 サイディングボード サイディングボードは外壁材の1つで、あらかじめ色や模様がつけられた製品を、現場で躯体に貼っていきます。 #gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-1 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-1 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */ 表面の模様やもちろん、凹凸や色も種類が豊富です。 モルタル #gallery-2 { margin: auto; } #gallery-2 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-2 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-2 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */ リシン仕上 モルタル外壁は、水・砂・セメントなどを混ぜたものを、現場で躯体に塗りその上から塗装を行います。 躯体の上にボードをはり、防水紙、金網(ラス)、その上からモルタルです。 外壁のパターンは、モルタル外壁を作る際にモルタルの上から塗装を行う工程でつけることができます。 パターンの種類は数十ともいわれ、色との組み合わせで考えると、仕上がりは無限にあります。 一方サイディングの場合は、あらかじめ模様や色がついているので、新築の現場では塗装を行うことはありません。 パターン付けに使われる道具 外壁のパターンにはいろいろな種類がありますが、使われる道具もさまざまです。 (出典:エスケー化研 ベルアートカタログ https://www.sk-kaken.co.jp/wp/wp-content/uploads/bellart.pdf) 吹き付け 骨材などを吹き付けて、表面をざらざら下仕上がりにする際には、ガンを使います。 吹き付け塗装ともよばれ、 ・リシン吹付 ・スタッコ吹き付け ・吹付タイル(ボンタイル) 等で使われます。 左官仕上げ #gallery-3 { margin: auto; } #gallery-3 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-3 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-3 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */ 左官ゴテを使って、いろいろな模様をかく工法です。 ・ウェーブ ・プロヴァンス など模様によって名前もあります。 櫛引 #gallery-4 { margin: auto; } #gallery-4 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 50%; } #gallery-4 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-4 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */ (出典:エスケー化研 ベルアートカタログ https://www.sk-kaken.co.jp/wp/wp-content/uploads/bellart.pdf) 櫛のような凸凹がついた櫛ごてを使えば、筋目状の模様を入れることができます。 凹凸がたくさんできるので、光の加減で美しい陰影が浮かび上がります。 パターンを付ける際の注意点 パターンは、塗料が完全に乾ききる前に、道具を使って模様を付けます。 そのため、サイディングのような機械的な模様というよりは、ランダムで自由な模様になり、 職人の技量がもろに出る工法になります。 塗装職人の中には、ローラーでサイディングしか塗ったことがないという人もおり、パターン付けを希望する場合は、得意な職人がいるかあらかじめ確認したほうがよいでしょう。 また、単に塗装するよりは手間がかかるため、塗装会社によっては別料金が必要になることもあります。 コストと仕上がりが満足いくものになるように、施工事例や口コミも確認して、パターン付けの塗装をしてくださいね。MORE