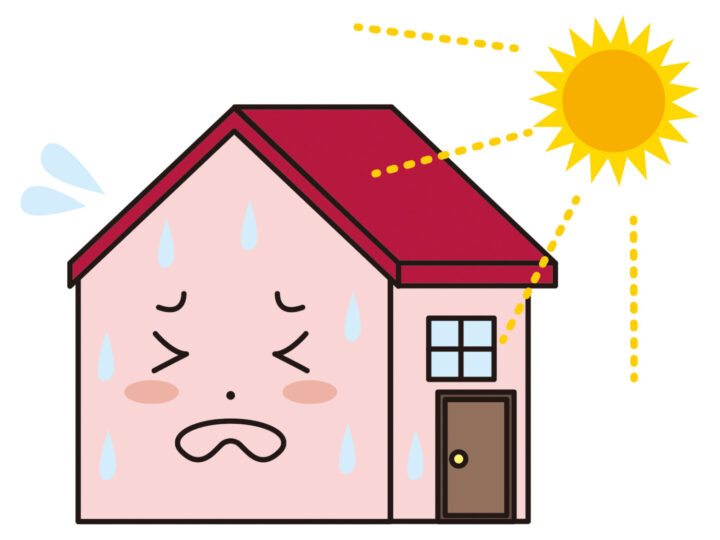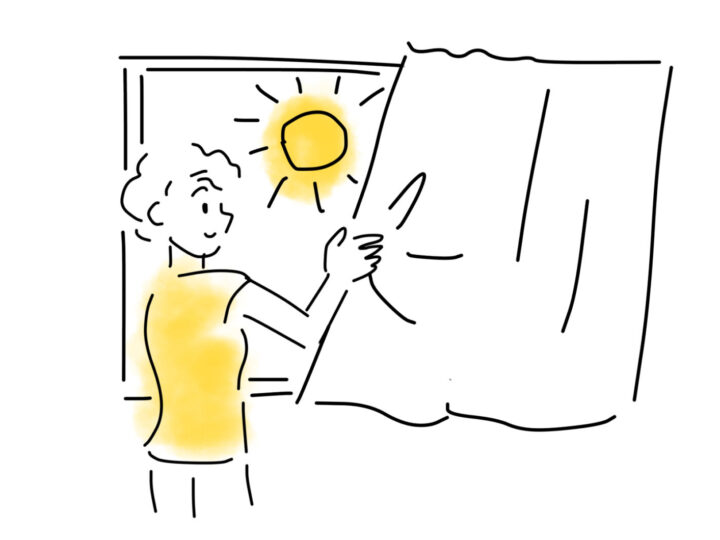
2023年9月21日 更新!
外壁塗装中はカーテンを閉める?工事中の生活について l塗り達
2023年9月21日 公開 外壁塗装中は、自宅で過ごすことはできるものの、好きな時に窓を開けるなど普段通りの生活が制限されることもあります。 外壁塗装の場合は足場を組んで作業を行うので、いつもは人がのぼってこられないような高い場所も職人が出入りします。 そこで気を付けておきたいのがカーテンです。 普段通り生活していたら、急に人が窓の外にいたらびっくりしてしまいますよね。 2階・3階など、いつもはカーテンを開けている窓の付近も塗装したりシール工事を行ったりするので、カーテンを閉めておく方がよいでしょう。 職人がカーテンが締まっていないからといって覗き見るようなことはありませんが、ベランダやバルコニーなども作業中に「これから入ります」「窓の近くへ行きます」等、都度声をかけるケースは少ないでしょう。 お互いに配慮するという意味でも、工事中職人がいるときはできるだけカーテンを閉めておいた方がよいでしょう。 そのほか工事中に生活面で気を付けておきたいこと カーテンを閉めておくことのほかに、工事中に気を付けておきたい生活のことをまとめます。 ①換気 冒頭にも出てきましたが、外壁塗装中は塗料の飛散を防ぐために窓にも養生を行います。 そのため、高圧洗浄時や塗装している最中には、好きな時間に窓を開けて換気をするのが難しくなります。 しかし、工事している2~3週間の間、まったく窓が開けられないのも換気面でも気持ちの面でも落ち着かないですよね。 あらかじめこの窓は開閉できるようにしておいてほしいというご希望や、換気が可能な時期や時間はいつかを打合せで確認しておくとよいでしょう。 ②エアコンの使用 工事中でもエアコンの使用は可能です。ただし室外機にも塗料の飛散を防ぐために養生を行うため、使用するエアコンをあらかじめ伝え吸排気ができるように養生してもらうようにしましょう。 完全に密閉された状態でエアコンを稼働させると不具合に原因になることがあります。事前に打ち合わせをしておきましょう。 ③洗濯物を屋外に干す 高圧洗浄などを行っているときは、洗濯物が濡れてしまうので屋外に干すことができません。 高圧洗浄は毎日行うわけではないので、限られた日程だけは干せないということになりますが、これも事前に確認しておくとスムーズに工事が行えるでしょう。 ④音 外壁塗装工事中は、いつもと違う音がどうしても出てしまう工程がいくつかあります。 例えば ・足場の設置と解体 ・高圧洗浄 など、人によっては「うるさい」と感じる場合もあります。 夜勤などで日中自宅でお休みになっている場合など、部屋割や作業内容によっては室内にいてもかなり音が響くことがあります。 上にあげた作業は、いずれも外壁塗装工事では必ず行う必要があるため作業をなくすことはできませんが、どのタイミングでどれくらいの時間音がするのか、事前に把握しておくとよいでしょう。 ⑤戸締り 外壁塗装工事中は、塗料の飛散を防いだり、職人の安全確保・作業効率確保のため足場を組んで、シートで建物を覆います。 そのため、外から中が見えにくい状態となり、工事関係者以外の立ち入りが感知しづらくなってしまいます。 職人が外から窓を開けて室内に入ることはありませんが、念のため2階や3階の窓も施錠し、戸締りをいつも以上にしっかりと行いましょう。 まとめ 外壁塗装工事の過ごし方について気を付けておきたい事柄を解説しました。 カーテンや施錠など、普段は行っていないことでも、ヒヤッとする前に気を付けておきたいですね。 工事前の打合せでは、工事中の過ごし方やこういうことはできるのかといった疑問も聞いて解消しておくとよいでしょう。MORE